今回は私の転職経験から、キャリアに悩むあなたに参考になればと思い記事を書こうと思いました。
共通点があれば、少しは力になれるかと。
私は6年目で総合商社から少人数ITベンチャーにジョインしました。
そんな私の元に、転職のプロセス、企業選びの基準などの話を聞きたいという前職の同僚、その繋がりでコンタクトを取ってくる人が最近増えています。
キャリアに悩んでいる人がそれだけ多いとみたいですね。
いつの時代も同じかと思いますが、最近は特に大手日系企業の社員がキャリアに悩んでいるようで、興味深くもあります。
色んな方から、毎回のようになぜ高待遇を捨ててまで転職したのかと聞かれ、答えている内にこうしてかつての私のように悩んでいる人がいっぱいいるのだなと実感します。



またこれを読んでいるあなたも悩んでいるからこそこの記事に辿り着いたのではないでしょうか?
私個人のキャリア、及び考え方が誰かの役に立てば、と思いここに記載することにしました。
本当に参考に過ぎませんが、少しでもキャリアに悩んでいる誰かのためになればと。
最初に私が圧倒的高待遇の中、転職を選んだ理由は「自由を手にし、その上で夢を追いかけることができる」人生を手に入れるためです。
Contents
なぜ大企業の高待遇を捨ててリスキーな道を? それでは理想の人生を手にできない
私は大企業に就職したわけですが、安定で高収入、ステータスも高い状況を手に入れました。
仕事自体は楽しかったのですが、この仕事をしていて将来自分の理想の人生を歩めるのだろうか? と疑問を持ち続けていました。
このままこの会社にいて将来理想の自分になれるのかという葛藤
実は将来は「時間に縛られない自由を手にしたい」「自分の好きなことを事業にしていきたい」という思いをずっと抱いていました。
そして、会社に入り、社会人2年目に偶然知り合いになった同年代の起業家と仲が良くなりました。
彼は自由な生活を送り、そして情熱を持って自分の事業に邁進しており、私に残した言葉は以下でした。
- まず、やりたいことをやるには時間と経済的自由を手にする必要がある。
- その自由を手にしない限り、いつまでも企業で労働集約型の仕事をすることになり、やりたいことができても実行が難しいし、時間が掛かる。
- この自由を手に入れてからの方が仕事が楽しくて、辛いこともあるけど情熱がある分踏ん張れる。
- 毎日が楽しくてしょうがない、事業を通じて感動を覚えることも多くなった。
この時に、熱く仕事の話をする姿は生き生きとしていてとても羨ましいと思いましたし、同時に自分もいつか私もこんな経営者になり、感動を積み重ねていける人生にしたいという気持ちが芽生えました。

そこで本当に商社でこのまま働いていて自分の理想像に近づいているのだろうか?
と自分に問いかけてみました。
もちろん会社で一生懸命仕事をすることにやりがいもありましたし、国家プロジェクトに携われるというのも大企業ならではの醍醐味でした。
しかし、商社で働いていてはもちろんやりたいことができる可能性は部署異動の問題から低く、投資先子会社の社長などやりがいはありそうですが、それは40代頃、本社の社長に万が一なれるとして50代後半、若しくは60代。
年功序列体制が色濃く残る会社では、会社社長をやるという面白い仕事をするにはどうしても「時間だけは」掛かってしまうことがわかっていました。
実際に私が担当していた仕事は「事業投資」であり、マーケットリサーチ、事業モデル作成、海外での交渉、と充実した日々は送っていました。
これも恵まれたことでもありますが、自分の理想とする人生に向かっていっている実感が持てなかったのです。




あえてリスキーな道を選ぶのではなく、リスクではない道で自分の理想の人生に近づける道を選ぶ

商社マンは異常な高給取りです。入社さえできてしまえばデスクに座っているだけでも6、7年目には残業代含めると1,000万円近い年収になります。
「Windows2000」という窓際族でも年収2,000万円の社員を表す言葉がありますが、こういった方々は本当にいました。
これが私は悪いことだとは全く思いませんし、むしろ大企業だからこそ彼らのような人間がいます。
「Windows2000」の方々の悪口も全く言うつもりもありません。人間はあるきっかけで「壊れる」んです。
パワハラを受けた、大きな仕事で失敗して強い責任感ゆえ引きこもってしまった、残業のしすぎで体を壊してしまった、などなど。
このような人たちが窓際で高い給料をもらっていても極論を言えば、それぞれの人に窓際に行かなければならない背景が絶対にあるので妥当だと思っています。
社員の高給取りの話に戻しますが、やはり他の業界よりも高い水準で給料をもらっていると、生活レベルに満足し、感覚が狂います。
自分自身も「自分はできる社員だ」と勘違いしてしまいそうな危うさがあります。

それはそれで、大企業は安定していますから、自分は自分のペースで進めば良いのでは?という意見もありますね。


それでも、自分の理想の人生に近づいておらず、「お金を稼ぐ」能力がつかない時間を積み上げていることに、ある種の恐怖感を覚えたのです。
これは私の周りをみての感覚ですが、同僚も3年目くらいまでは仕事に対する意識が高い人が多いですが、5年目くらいになってくると急激に安定志向に入る人がとても多かったです。
流されずに自分の目標に向かって努力ができる人はそのまま会社に残るのが一番でしょう。
ITベンチャーへの転職は自分の理想像に近づくための仕事ができる場所、必死に仕事をしている人達が多い場所の方が希望する業界で学ぶこともでき、キャリア的により大きなプラス成長が見込めると思いました。
私の中では、大企業に守ってもらっていることこそが「リスク」だったんですよね。
昨今AIで仕事が奪われるという話が大きく報道されていますよね。
これはリアルにこれからも伸びる業界にいないとブルーワーカーの仕事しかできないようになってしまう不安もあります。
だからこそ、大きく成長できる、これからも伸びる業界に身を置くのは非常に重要だと思っています。


日系企業では自分の希望部署に行くにはタイミング、運が必要

総合商社の場合、希望していない部署に配属となり、2-3年と長期に亘り他の部署に抜け出せないことも多々あります。
私自身は運が良く、完全に希望通りにはいかなかったものの、第二希望くらいの部署を短期間で3つ経験しました。
これはいろんな経験ができたので本当に幸運で、部署異動が多いのはありがたく思う方が良いというのは起業家のけんすうさんも別記事で触れていますね。
関連記事>>>【起業家思考】けんすうさんが語る「これからの優秀な人」
会社の内情をみていると、社員が全く希望していない部署に配属になり、3年嫌々仕事をするというパターンを多く見てきました。
ローテーションが主軸の大企業勤務の宿命とも言えますが、私自身も将来的にそのリスクはあるだろうと思っていました。
商社の場合はビジネス分野の幅が広く、エネルギーを希望していたのにヨーグルトを扱っている先輩もいますし、ワインがやりたかったのに資源関係の仕事をしている人もいます。
商社の人の特徴は、もの自体には興味がなく、ビジネスすること自体が好きな人が多いことです。
しかし、希望の商品や業界がある人の場合は、自分のキャリアコントロールが難しく、自分の希望する仕事を転職で掴み取るこ方が早いです。
私自身、入社前は特段希望していた商品はなかったのですが、入社2年目から一貫してIT業界の仕事をしたいと考えていて、社内でも希望を出してみましたがローテーションの兼ね合いでしばらくは保留とのことでした。
これはひとえにタイミングの問題もありますし、業界を超えての部の横断は難しいのが実情です。
希望通りの部署にいっている人はかなりの強運と社内コネクションがある人です。
粘って行きたい部署に行けるまで待てば?とこれもいろんな人に言われましたが、私には待っている時間ももったいないと思ってしまうし、
一時的に高収入は失いますが、将来を見据えて希望する仕事(業界)、成長曲線、自分の将来の理想の姿への距離と今の高給で天秤にかけた際、転職することを決意しました。
会社の成長を直に感じたい、現役経営者のそばで働きたい
前記事でも書きましが、大企業で働いていると自分の担当している案件がどれだけ儲かっても実感が全くないんです。
その儲けは会社の規模からすれば大きくなく、会社の成長を感じることができたことはありませんでした。
何千億円のプロジェクトにも携わらせてもらいましたが、分業制が敷かれているので個人の喜びはそこまで大きくないのは他社員も同じだと思います。
加えて、大きな損失を被った時も会社は盤石なので「自分ごと」にするのがとても難しいです。
「自分ごと」にしなければ稼げる力もつかず、経営者として舵を取れる人間になることは限りなく難しいと考え、転職活動ではITベンチャー、スタートアップも受け始めました。

熱く仕事をする経営者のそばで、思いっきり夢を語りながら事業に邁進する企業を探し、あるITベンチャーに転職し、生きたスキルをつけていくことにしました。
この記事を読んでくれている方の中では結局他力本願じゃんとか、大企業でもっと偉くなればいいじゃん、という意見はあると思います。
しかし、大企業に不満があるというより、私が転職したのは近い将来に理想の自分になりたいという完全な「エゴ」なんです。
そのエゴを受け入れてくれた会社が今の会社です。
経営者のそばで働いている今は、本当に経営の極意、判断基準など多くのことを学べていますし、なんとか自分が力になれないか、と頭を凝らす日々です。



・〜Twitter界隈の声〜
これは参考ですが、Twitter界隈で他にも大企業勤務を続けることに疑問を投げかけているツイートです。
色んな見解がありますね。但し、Twitterの声はまだまだ日本ではマイノリティの意見です。
かなり尖った発言をする人が多いのでいくつか気づきは得られるかと思います。
なんとなく、私の元にキャリア相談に来る人たちが増えた理由もわかる気がします。
インターネットは格差拡大させます。目立ってるやつを業界で干す、理不尽な上司がピンハネする、伝統と称して下積みを強要する、これらの再分配機能がないからです。一握りの人たちに際限なく富が集まります。
— Kazuki Fujisawa (@kazu_fujisawa) 2017年8月28日
若手商社マンの退職が増えてきて、商社側はいずれ辞めるかもしれない尖った人材の採用に慎重になってる。一方、優秀な学生の志向性は「商社orコンサル」から「コンサルorイケてるベンチャー」へシフトしてる。この商社離れともいえる現象が商社の保守化を加速させ、商社は時代から取り残されそう。
— Tsukasa (@tsukapon127) 2017年7月13日
元商社マンNightは、商社を辞めて現在スタートアップをやってる人に話を聞く、かなりベンチャーなイベントだったんだけど、まだ入社3ヶ月くらいの総合商社マンが何人か参加してたのには笑った。
「入社してリアルに感じたんですよ。商社の未来は無いなって。」
— 木村 匠吾 (Shogo Kimura) (@imshogo) 2017年7月12日
総合商社の10年目までは横並びの下積み期間という成長のスピードの遅さが嫌で辞めてジョブ型のベンチャーやコンサルに転職する若手のケースをいくつか聞いてる。ジョブ型の会社で10年続けていたら立派な第一人者になれるし、3年程度で得たいスキルを身に着けて次のステップにもいきやすい。
— Kotaro Higuchi (@happytarou0228) 2017年7月7日
会社を始めた時周囲に「大丈夫、潰れてもスタートアップが企画部長で雇ってくれるから」と言われ、実際そうやって生活する人が多くいることを知ったが、自分で戦略を決められる自由を知った今人の会社で働ける気がせず。結果として退路は絶たれた。https://t.co/6AhPbuEJp7
— Umemoto, Yukari (@umemotoyukari) 2017年6月17日
総合商社なんて中途入社が増えて年功序列が崩れたら、先輩は後輩に教えなくなる。特に商品の売買をやる部署は、暗黙知で食ってるわけだから、これは致命的だわな。まあ、心配しなくても、商社が事業投資型にシフトしきって、商品の売買を捨てれば、生え抜き社員の暗黙知なんか何の役にも立たなくなる。
— 総合商社の中の人 (@shukatsushosha) 2017年6月16日
入社から20年。40代前半でようやく課長、ちなみに裁量権はない。50前後でようやく部長、ちなみに裁量権はない。55-58歳で本部長、ここで漸く多少の裁量権が出てくるがそれでも役付役員の発言次第。
それを見た若手、中堅がこぞって辞めていて中途採用をガツガツかけているのが実態やぞ。
— 物流太郎(LOGITARO) (@LOGITARO1) 2017年6月4日
まさに29歳の時にこれ考えてた(会社員時代)。
そして「このままじゃ40歳のおれヤバい」って思ったので、次のこと何も考えずに、とりあえず辞めた。 https://t.co/EJ1SHk1Zcz
— 芳野真弥 Imaginary Love (@m_t_t_b) 2017年8月14日
企業の規模が大きくなればなるほど社内規則は厳しくなり、出る杭は打たれる保守的な組織になる。僕が今までに会った中で1番活き活きと仕事の話をしていたのは商社業界では五大ではなく皮肉にも双日、専門商社の方々。会社をどんどん辞めるのが財閥系商社。
— 伊藤哲士 (@tetsushi_ito) 2017年8月29日
私自身が商社出身なのでかなり商社関連に偏っていますが、基本的には大企業にも当てはまります。
具体的な転職プロセス

私の転職活動の始まりは、BIZREACHに登録した日でした。
今だと普通ですよね?私のところにキャリア相談に来る社員はみんな登録してて、それを前提に聞きにきます・・・。(笑)
サイトの活用方法ですが、私はこの他にDODA、リクナビNEXTも活用し、BizReachは外資系や、ITベンチャー企業メイン、日系大企業はDODA、リクナビNext、スタートアップはたまにWantedlyも利用していましたね。
この辺はまだ転職活動を考えていない人に向けても参考になる内容を書いていますので、読んでみてください。




実際に転職面接で評価されたのは?

私の商社でのキャリアは入社後2年間はバリバリの物流部署、その後2年半国内の子会社に出向し営業(プロジェクトリーダー)、一部人事管理、その後本社で資源投資部署2年の計6年でした。
転職活動(面接の練習はかなりしましたが)は概ねうまくいき、商社での経験した仕事も少し考慮されました。
商社に勤めている人間はジェネラリストを育てるのが会社方針なのでどうしても専門性がありません。
私の扱っている商品も2年ごとに変わっていましたからそれはそうですよね。
ですので悲しいことを言うと、基本的に私がオファーを貰えた理由はポテンシャルの部分でした。
私の少し考慮された商社での経験に関しては以下のようなものです。
投資部署で案件組成経験
外資コンサルは採用面接の際に特にこの点を良く見ていた気がしました。
投資スキーム検討、投資までのプロセス、投資後の経営を見据えた議論等コンサル業務と重なる部分が非常に多いそうです。
商社で投資部署にいた方はコンサルには転職しやすいのかもしれません。
フェルミ推定の準備だけは怠らずに。
チームマネジメント経験
国内の子会社に出向していた頃に、営業チームを作ってそのリーダーとして仕事を進めることが多かったです。
部下と呼んでいいのかわかりませんが、子会社のプロパー社員6人に指示を出して仕事を進めるという役割でした。
積極的にどのような工夫をしてチームを動かしてきたかという点、どの会社にもかなり深堀りされました。



まとめ:ITベンチャー企業転職後の今感じること

まだ数か月ですが、今のところ転職は正解だった、というより自分に合う企業と巡り会えたと思っています。
給料こそ少し下がりますが、思いっきり少人数の会社のマネジメントに入って仕事をしていますし業績によっては自分の給料も跳ね上がります。
今まで大企業で働いていては気づかなかった会社名、資本の厚さによる商売作り、雇用、新規情報獲得のアドバンテージを実感しましたが、それがない分自分たちで仕事を作り上げていくプロセスの醍醐味、何よりも社員同士で熱く語り合えることが増えました。
もちろん、ヒリヒリする感覚も多々ありますし、チーム員に叱られることもありますが、着実な成長、理想の自分に近づいている実感があります。
キャリアの相談を受けていて、私が商社で働く人には2パターンの属性があるなと感じています。
- 自分が起業しても集められない金、人、情報を使って国家プロジェクトに携わっていくことが生きがいという人
- 早く一人前の商人になって独立したい人
昨今若手の商社離れが進んでいますが、悩んでいる人は自分がどっちの立場で余生を過ごしたいかを考えるのが第一かもしれません。
あなたのキャリアが、より充実したものになりますように。
以上、私の総合商社からのキャリアチェンジした理由とその転職プロセスについて。なぜ大企業の高待遇を捨ててリスキーな道を?…でした!








 BIZREACH
BIZREACH 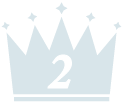 doda
doda  リクナビネクスト
リクナビネクスト 